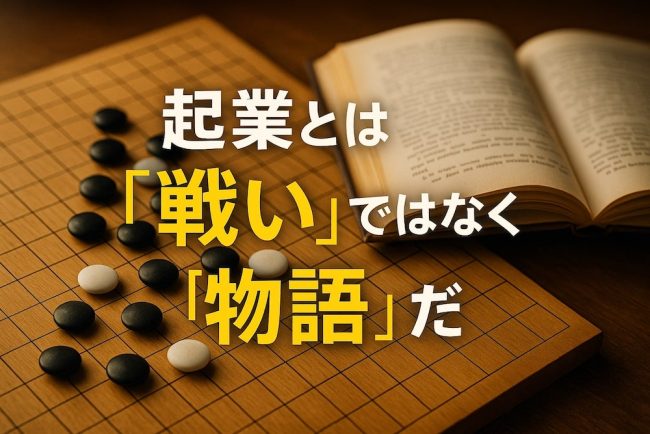「たかの友梨って、CMでよく見るけど実際どうなの?」
「エステって勧誘がすごそう…」
「1回で本当に効果があるの?」
エステに興味はあるけれど、たくさんの不安や疑問があって一歩踏み出せない。
そんな風に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、美容ライターである私が実際に「たかの友梨ビューティクリニック」のフェイシャルエステを体験し、感じたことを忖度なくレビューします。
サロンの雰囲気から施術内容、気になる効果、そして勧誘のリアルなところまで、あなたの知りたい情報をすべて詰め込みました。
この記事を読めば、たかの友梨があなたに合うエステサロンなのか、きっと判断できるはずです。
たかの友梨のフェイシャルエステを体験!まずは結論から
先に結論からお伝えします。
たかの友梨のフェイシャルエステは、「技術力と非日常的な空間を重視し、自分へのご褒美として本格的なケアを受けたい人」に、自信を持っておすすめできます。
施術後の肌は、自分で触れるのが嬉しくなるほどモチモチになり、鏡を見るたびに気分が上がりました。
一方で、料金は決して安くはなく、施術後のコース提案(勧誘)も確かにありました。
この記事では、そうした良い面も気になる面も包み隠さずお伝えしていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。
たかの友梨ってどんなエステサロン?3つの特徴
まずは、「たかの友梨ビューティクリニック」がどのようなエステサロンなのか、その特徴を3つのポイントでご紹介します。
特徴1:世界中の美容法を取り入れた多彩なコース
たかの友梨の最大の特徴は、創業者であるたかの友梨氏自身が世界中を旅して見つけ出した、最先端の美容技術や伝統的な美容法を積極的に導入している点です。
フェイシャルだけでも、エイジングケア*¹、美肌ケア、フェイスラインケアなど、悩みに合わせて非常に多くのコースが用意されています。
例えば、韓国で人気のピーリング技術を取り入れたコースや、ハワイの伝統的な手法を活かしたトリートメントなど、他ではなかなか体験できないユニークなメニューが豊富です。
これだけ選択肢があれば、自分の肌悩みにぴったりの施術が見つかるはずです。
*¹ 年齢に応じた肌のお手入れのこと
特徴2:「愛といたわりの精神」に基づくハンド技術へのこだわり
たかの友梨は「愛といたわりの精神」を経営理念に掲げています。
その理念は、エステティシャンの技術力にも表れています。
最新のマシンも導入されていますが、基本はエステティシャンの手による丁寧なハンドテクニックを重視。
厳しい研修と技術検定をクリアしたエステティシャンのみが施術を担当するため、技術レベルが高いと評判です。
実際に施術を受けてみると、その指の動き一つひとつに熟練の技を感じ、機械だけでは得られない深いリラクゼーション効果を実感できました。
こうした高い技術力を支えているのが、たかの友梨で働く社員一人ひとりへの充実した教育体制です。
たかの友梨では、未経験からでもプロのエステティシャンを目指せるよう研修制度に力を入れており、たかの友梨の社員として働くことに興味がある方向けの求人情報でも、その手厚いサポート体制が紹介されています。
特徴3:日常を忘れさせるゴージャスな空間
サロンに一歩足を踏み入れると、そこはまるで高級ホテルのような非日常空間。
エレガントで上質なインテリア、清潔に保たれた室内は、いるだけで気分を高めてくれます。
施術を受ける個室もプライベートが保たれており、心からリラックスできる環境が整っています。
エステは肌をきれいにするだけでなく、心も癒すもの。
たかの友梨は、そんなトータルな美しさを提供してくれる場所だと感じました。
私が体験したフェイシャルコースの流れを徹底レポート
ここからは、私が実際に体験したフェイシャルエステの予約から施術後までの流れを、順を追って詳しくレポートします。
Step 1: 予約はWEBから簡単申し込み
予約は、たかの友梨の公式サイトから行いました。
体験したいコースを選び、希望の店舗と日時を入力するだけの簡単なステップです。
申し込み後、店舗のスタッフから予約確認の電話があり、その際に簡単な質問や当日の持ち物について丁寧に説明してくれたので、初めてでも安心できました。
Step 2: 来店~丁寧なカウンセリング
予約当日に店舗へ伺うと、まず豪華なウェイティングスペースに通され、ハーブティーをいただきながらカウンセリングシートを記入します。
その後、カウンセリングルームでエステティシャンの方と一対一で肌の悩みや生活習慣について詳しく話をしました。
私が特に気にしていた「乾燥による小じわ」と「頬の毛穴の開き」について伝えると、私の肌状態を細かくチェックした上で、最適な施術プランを提案してくれました。
一方的な説明ではなく、こちらの話をじっくり聞いてくれる姿勢に好感が持てました。
Step 3: いよいよ施術開始!気になる内容は?
カウンセリング後は、専用のガウンに着替えて施術ルームへ。
私が体験したのは、保湿とエイジングケア*¹を目的としたコースです。
- クレンジング&洗顔:
自分では落としきれない毛穴の奥の汚れまで、スチームを当てながら丁寧にオフしてくれます。 - ハンドトリートメント:
たかの友梨こだわりのハンドテクニックで、顔からデコルテ、肩、背中までじっくりとマッサージ。絶妙な力加減が本当に気持ちよく、思わず眠ってしまいそうになるほどでした。 - マシンケア:
肌悩みに合わせた美容液を、専用のマシンを使って肌の奥(角質層)まで浸透*⁴させていきます。 - パック:
最後に、肌の状態に合わせた美容成分たっぷりのマスクで潤いを閉じ込めます。パック中はフットケアもしていただき、全身リラックスできました。 - お仕上げ:
化粧水やクリームで肌を整えて、施術は終了です。
*¹ 年齢に応じた肌のお手入れのこと
*⁴ 浸透:角質層まで
Step 4: 施術後の肌チェックとアフターカウンセリング
施術後は、パウダールームで身支度を整えます。
化粧品やドライヤーなどが自由に使えるので、エステ後に出かける予定があっても安心です。
その後、再びカウンセリングルームでアフターティーをいただきながら、施術後の肌状態をエステティシャンと一緒に確認。
今後のスキンケアに関するアドバイスももらえました。
この時に、継続して通うためのコースや料金プランの説明があります。
【本音レビュー】たかの友梨フェイシャルの効果と感想
さて、ここからは皆さんが一番知りたいであろう、私の「本音」のレビューです。良かった点、気になった点を正直にお伝えします。
良かった点:1回でも感じられた効果と特別感
まず、施術の効果には非常に満足しています。
施術直後、鏡を見て驚いたのは肌のトーンがワントーン明るくなっていたこと。
気になっていた頬の毛穴もキュッと引き締まり、触ると吸い付くようなモチモチ感がありました。
この効果は翌日以降も数日間続き、化粧ノリが格段に良くなったのを実感しました。
また、ゴージャスな空間でプロの施術を受けるという「特別感」は、日々の疲れを癒す最高のご褒美になりました。
気になった点:料金と勧誘について
一方で、気になった点も正直にお伝えします。
一つ目は料金です。
正規のコース料金は、他のエステサロンと比較してもやや高めの設定だと感じました。
継続して通うには、ある程度の予算が必要です。
二つ目は、やはり勧誘です。
施術後のアフターカウンセリングで、コース契約の提案がありました。
「しつこい」と感じるほどではありませんでしたが、「今日契約すればお得になります」といった形で、いくつかのプランを提示されました。
ただ、私が「一度持ち帰って検討します」と伝えると、それ以上強く勧められることはありませんでした。
もし勧誘が不安な方は、「家族に相談します」「予算的にすぐには難しいです」など、きっぱりと断る意思表示をすることが大切です。
総合評価:こんな人におすすめ!
以上の点を踏まえて、たかの友梨のフェイシャルエステは以下のような人におすすめです。
| おすすめな人 | あまりおすすめできない人 |
|---|---|
| 1回でも確かな効果を実感したい人 | とにかく安さ重視でエステを探している人 |
| プロによる本格的なハンド技術を受けたい人 | 勧誘されるのが絶対に嫌な人 |
| 高級感のある非日常的な空間でリラックスしたい人 | サクッと短時間で施術だけを受けたい人 |
| 自分へのご褒美として、贅沢な時間を過ごしたい人 | スタッフとのコミュニケーションが苦手な人 |
たかの友梨フェイシャルの口コミ・評判を徹底分析
私一人の感想だけでなく、より客観的な評価を知るために、SNSや口コミサイトでの評判を調査しました。
良い口コミ:技術力の高さと効果を実感する声
良い口コミで最も多く見られたのは、やはり技術力の高さと効果に対する満足の声でした。
「施術がとても丁寧で、気持ちがよかったです。施術後にはお肌が白くモチモチになっていて感動しました。」
「リラクゼーションの一環としても活用しているので、心身共にリラックスできる空間。」
「徹底したカウンセリングで、一人ひとりの悩みに寄り添い、オーダーメイドの施術プランを提案してくれる。」
やはり、長年の実績に裏打ちされた技術力と、個々の悩みに向き合う姿勢が高く評価されているようです。
悪い口コミ:勧誘や料金に関する不満の声
一方で、ネガティブな意見としては、勧誘や料金に関するものが目立ちました。
「終わった後の勧誘でとても不快な気持ちになりました。会員になることを勧められ、学生で金銭面的に厳しいので…と断らせていただきました。」
「何よりも高い。本当に高い。勧誘みたいなものはなかったけど、痩せられなかった時の絶望感がやばいです。」
「施術はいいのに、終わった後の商品勧誘がきつい。」
勧誘の強度は店舗や担当者によって差があるようですが、ある程度の提案は覚悟しておいた方が良さそうです。
また、高額な料金に見合う効果を感じられなかったという声も一部で見られました。
目的別!たかの友梨のおすすめフェイシャルコース
たかの友梨には豊富なフェイシャルコースがあります。 ここでは、代表的なお悩み別におすすめのコースをいくつかご紹介します。
エイジングケア*¹なら「ヒトカンフェイシャル」
年齢による肌悩みが気になる方におすすめなのが、ヒト幹細胞培養液抽出物*⁵を贅沢に使用した「ヒトカンフェイシャル」です。
最新の美容マシンとハンドテクニックを組み合わせ、ハリと潤いに満ちた肌へと導きます。
*¹ 年齢に応じた肌のお手入れのこと
*⁵ ヒト臍帯血細胞順化培養液の上ずみを抽出使用(保湿成分)
毛穴・くすみが気になるなら「白玉つや肌*²フェイシャル」
超音波とイオンの力で毛穴の汚れを洗浄するマシンと、ヒトサイタイ血幹細胞順化培養液*⁶を高濃度に配合した美容液を使用する贅沢なコースです。
自宅のケアでは落としきれない頑固な毛穴汚れにアプローチし、内側から輝くようなクリアな肌を目指します。
*² 白玉のようなやわらかい肌のこと
*⁶ 上ずみを抽出使用(保湿成分)
リフトアップ*³を目指すなら「蜘蛛の巣ネットアップフェイシャル」
蜘蛛の糸のタンパク質繊維⁷を配合したクリームと、サケの白子のDNA抽出成分⁷配合の美容液を使用したユニークなコース。
たかの友梨ならではのテクニックで、ハリ・うるおいを失った大人肌にアプローチし、ピンとした上向きの印象へと導きます。
*³ 施術動作の表現
*⁷ 保湿成分
たかの友梨の料金体系と予約・解約方法
最後に、たかの友梨を利用する上で知っておきたい料金体系や各種手続きについて解説します。
会員料金とビジター料金について
たかの友梨には会員制度があり、会員になるとビジター(非会員)よりもお得な料金で施術を受けられます。
継続して通うことを考えている場合は、入会を検討するのがおすすめです。
もちろん、都度払いのビジター利用も可能です。
初回限定!お得な体験コースを活用しよう
「いきなりコース契約は不安…」という方のために、たかの友梨では多くのコースで初回限定のお得な体験価格が設定されています。
正規料金の半額以下で試せるコースも多いので、まずは体験コースでサロンの雰囲気や施術内容を確かめてみるのが賢い選択です。
予約・変更・キャンセルの方法
予約は公式サイトのWEBフォームまたは電話で行えます。
予約の変更やキャンセルを希望する場合は、予約日の前日までにサロンへ直接連絡が必要です。
当日キャンセルや無断キャンセルの場合はキャンセル料が発生することがあるため、注意しましょう。
解約・クーリングオフについて
万が一、コース契約後に解約したくなった場合でも、クーリングオフ制度や中途解約の制度が設けられています。
手続きに不安がある場合は、専用の「ご契約相談センター」に問い合わせることができるので安心です。
まとめ:たかの友梨は一度体験する価値あり!技術と空間に癒される本格サロン
今回は、たかの友梨のフェイシャルエステを忖度なしでレビューしました。
確かに料金は安くなく、コース提案もありますが、それを上回る確かな技術力、目に見える効果、そして心から癒される非日常空間がそこにはありました。
毎日頑張っている自分へのご褒美として、あるいは特別なイベント前のスペシャルケアとして、一度体験してみる価値は十分にあります。
お得な初回体験コースを利用して、ぜひあなた自身の肌でその効果を確かめてみてください。